 セキュア女子
セキュア女子山のような資料。終わらない議事録チェック。
「もっと住民対応に時間を使いたい!」
でも、話題のAIはセキュリティが不安…。
そんなあなたに知ってほしいのが、
GoogleのAIアシスタント 「NotebookLM」。
- 学習にデータを使わないと公式明言
- 自治体データを守る設計が前提
実績も出ています。
例:京都府舞鶴市で年間約800時間削減を試算。
この記事でわかること👇
- ChatGPTとどう違う? NotebookLMの実力
- 情報漏洩・データ管理の不安をどう解消するか
- 「資料の山」を宝に変える具体的活用シーン(事例つき)
「導入や運用が難しそう…」という心配も不要。
後半では、
- 明日から始める導入5ステップ
- 無料プランの賢い選び方
- 精度が劇的に変わるプロンプト設計のコツ
- 庁内で“使われ続ける”定着のコツ
読めば、明日からの業務が軽くなるヒントが見つかります。
あわせて読みたい
NotebookLMだけでなく、他の自治体向けAIも含めて「安全に選ぶ基準」を押さえておくと、庁内説明が一気に楽になります。稟議に使えるチェックリスト付きの記事はこちら。


自治体データを守る、NotebookLMのセキュリティと可能性
情報漏洩とデータ管理、最大の懸念点を解消


AIと聞くと、まず「入力した大切な情報が、どこかに漏れてしまわないかしら?」と心配になりますよね。各自治体で定められている個人情報保護条例や、厳格なセキュリティポリシーを考えると、その懸念はとても大きなものだと思います。
結論からお伝えしますと、NotebookLMは、私たちが提供した資料をGoogleがAIの学習(トレーニング)に利用することはない、と公式に明言しています。これは、Google WorkspaceやGoogle Cloudが準拠する、国際的なセキュリティ認証(ISO/IEC 27001など)にも裏付けられた堅牢なインフラの上で提供されており、私たちが安心して使えるように技術的・倫理的に配慮されている点なんです。
出典1: Google Workspace の生成 AI に関するプライバシー ハブ
出典2: Google Cloud コンプライアンス ポータル
つまり、庁内の会議の議事録や個人情報を含む相談記録などをアップロードしても、それがAIモデルの性能向上のために使われたり、外部に意図せず公開されたりすることはないのですね。データはご自身のGoogleアカウントに紐づいて厳格に管理されます。
ただし、一つだけ注意したい点があります。それは、私たち自身の「使い方」です。株式会社東京商工リサーチが2024年に発表した調査によると、2023年に上場企業とその子会社で発生した個人情報漏洩・紛失事故の原因のうち、「ウイルス感染・不正アクセス」が55.4%と最多であったものの、次に「誤操作」(24.2%)、「紛失・盗難」(15.5%)と、人的な要因が大きな割合を占めていることがわかります。
例えば、組織で管理されていない個人のGoogleアカウントで機密情報を扱ったり、共有設定を誤って「一般公開」にしてしまったりするケースです。
LGWAN環境や「学習に使われない」運用の確認など、自治体ならではの注意点をさらに深掘りしたい方はこちらもどうぞ。NotebookLMと併せて比較観点を整理できます。


ChatGPTとは違う、自治体業務での本当の実力
皆さんもよくご存知のChatGPTは、新しい企画のアイデアを出してくれたり、文章を考えたりする「創造的な壁打ち相手」として、まるで物知りの博士のように頼りになりますよね。ですが時には、事実とは違う「それらしい答え」を返してきて、業務で使うには少しハラハラしてしまう場面もあったかもしれません。
一方、NotebookLMは、そうした一般的なAIとは役割が異なります。NotebookLMの最大の実力は、私たちがアップロードした資料の内容「だけ」を完璧に理解し、その範囲内で答えを返してくれるという、まるで誠実な専門家のような性格にあるんです。
なぜなら、NotebookLMは「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術を基に作られているからです。これは、AIのパワフルな「脳(大規模言語モデル)」と、私たちが用意した「専用の図書館(資料データ)」を連携させるような仕組み。世の中の曖昧な情報ではなく、あくまで手元の資料に書かれている事実だけを根拠にするため、AIが勝手な想像で話を作り出す「ハルシネーション」という現象を大幅に抑制できるのが大きなメリットです。
参考: Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks (RAG技術の原論文)
例えば、新しい職員さんが住民の方から「〇〇地区の粗大ごみの申請方法について知りたい」と質問されたとします。このとき、市の公式ウェブサイトやごみ収集に関する最新の条例PDFをNotebookLMに読み込ませておけば、ベテラン職員さんのように、その資料に基づいた正確な手順や手数料を即座に回答として生成できます。
ただし、注意点もあります。NotebookLMは資料に書かれていないことは答えられません。もし条例が改正されたのに古い資料を読み込ませてしまうと、AIは悪気なく古い情報を答えてしまいます。常に最新の正しい情報を「専用の図書館」に入れてあげることが、この誠実な専門家を活かす秘訣なのです。
年間800時間削減、舞鶴市の成功事例に学ぶ
「新しいツールを導入しても、本当に効果があるの?」というのは、担当者として一番気になるところだと思います。そんな時、同じ立場の他の自治体の成功事例は、とても心強いですよね(これは「あの市がやっているなら大丈夫だろう」と感じる、心理学でいう「社会的証明」の効果なんですよ)。
ここで、京都府舞鶴市の素晴らしい事例をご紹介します。舞鶴市では、職員からの内部問い合わせ対応という、どの自治体にもある身近な課題解決にNotebookLMを活用しました。
これまでは、何か不明点があると職員が600ページ超のマニュアルをめくったり、総務課へ電話したりしていました。これは、質問者の時間を奪うだけでなく、回答する総務課職員の業務を中断させる「両者にとっての課題」だったそうです。
そこで舞鶴市は、この膨大なマニュアルや過去の通達文書をNotebookLMに読み込ませ、職員専用のAIチャットボットを構築。特別なシステム開発ではなく、既存のツールを工夫して活用したのです。
その結果、これまで平均5分かかっていた情報検索が、わずか30秒ほどに短縮。実に90%もの時間短縮を達成し、職員さん一人ひとりの小さな『探しものの時間』が、市全体で集まると年間800時間(約100人日)という、一人の職員が約5ヶ月間かかるほどの大きな価値に変わると試算されました。
この取り組みは、単なる時間削減に留まりません。デジタル庁が推進する「BPR(業務改革)」、つまり、これまでのやり方を見直して、より価値の高い業務に職員が集中できる環境を作るという、まさに国が進めるDXの考え方を体現したモデルケースと言えるでしょう。
「資料の山」が宝に変わる、具体的な活用シーン
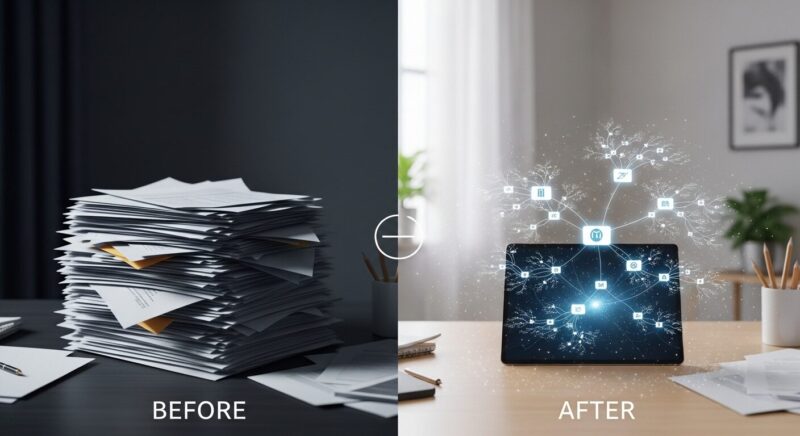
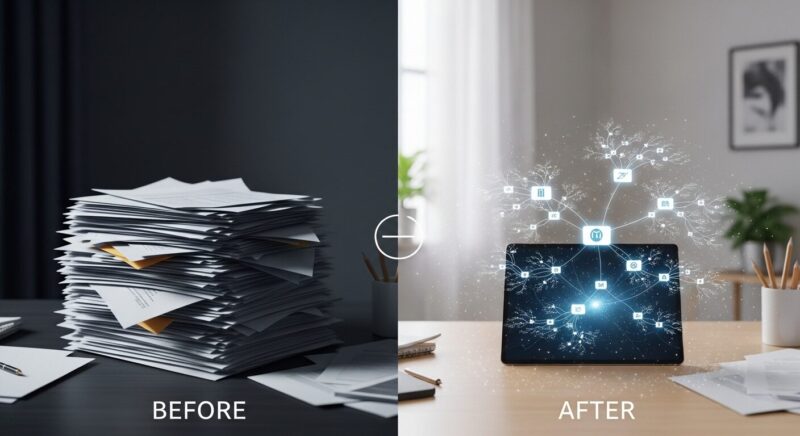
机の引き出しや共有フォルダに眠っている、あの膨大な量の議事録や報告書…。一つひとつは大切な記録ですが、量が多すぎて「どこに何が書いてあるかわからない」状態になっていませんか?
NotebookLMは、そんな「資料の山」を、自治体の誰もが活用できる「知識の宝」に変えてくれるツールです。RingCentral社の2024年の調査によると、労働者は平均して1日に13回もアプリを切り替えて情報を探しており、多くの時間がこうした非生産的な作業に費やされています。この時間を削減できるだけでも、大きな価値がありますよね。
出典: RingCentral Survey Finds App Overload Crushing Employee Productivity (eWeek)
具体的にどのような活用シーンがあるか、日常業務をイメージしながらいくつかご紹介します。
- 議事録からの決定事項リストアップ
長時間の会議の音声データを文字起こししたテキストファイルをNotebookLMに読み込ませ、「この会議での決定事項と、それぞれの担当者をリストアップして」とお願いするだけで、要点をまとめた報告書が瞬時に完成します。もう一度会議の録音を聞き直す必要はありません。 - 住民アンケートの分析と要約
数百件にも及ぶ住民アンケートの自由記述欄のテキストをすべて読み込ませ、「子育て支援に関するポジティブな意見とネガティブな意見をそれぞれ要約して」と指示すれば、次の施策につながる貴重なヒントを客観的に抽出できます。 - 複雑な条例・規則の平易な解説作成
専門用語が多くて分かりにくい条例の全文を読み込ませ、「この条例のポイントを、中学生にも分かるように説明する文章を作って」と依頼すれば、住民向けの説明資料やウェブサイトの原稿を考える時間を大幅に短縮できます。これは、専門家であるほど専門用語で考えてしまう「知識の呪い」という心理的な壁を乗り越える手助けにもなります。 - 異動時の引き継ぎ資料の作成サポート
前任者が残した大量の引き継ぎ資料や過去の文書をすべて読み込ませ、「〇〇事業の背景と過去の経緯を時系列でまとめて」と指示すれば、異動後すぐに業務の全体像を把握するための自分専用の資料が作れます。
このように、これまで「読むのに時間がかかる」と敬遠されがちだった一次情報に、誰もが瞬時にアクセスし、対話できるようになること。これが、NotebookLMがもたらす最大の価値かもしれません。資料は、ただ保管するだけの「記録」から、未来の業務を助ける「知識」へと変わっていくのです。
NotebookLM導入を成功へ導く、自治体の実践ステップ
PCが苦手でも大丈夫、明日から使える導入5ステップ


「新しいツールって、覚えるのが大変そう…」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、どうぞご安心くださいね。NotebookLMを始めるのに、専門的な知識や難しい設定は一切必要ないんです。
その理由は、普段私たちが使っているウェブブラウザ(Google Chromeなど)の上で、すべての操作ができてしまうから。特別なソフトをパソコンにインストールする必要もありません。
それでは、まるで新しい文房具を使い始めるような気軽な気持ちで、さっそく5つのステップを見ていきましょう。
- ステップ1:Googleアカウントでログインする
まずは、NotebookLMの公式サイトにアクセスします。画面が表示されたら、いつもお使いのGoogleアカウントでログインするだけ。これで準備の半分は完了です。 公式サイト: Google NotebookLM(https://notebooklm.google.com/) - ステップ2:「新しいノートブック」を作る
ログインすると、本棚のような画面が表示されます。ここで「+ 新しいノートブック」というボタンをクリックしてみましょう。これから情報を整理していく、あなた専用のノートができました。 - ステップ3:資料(ソース)をアップロードする
次に、AIに読んでほしい資料をアップロードします。PDF、テキストファイル、Googleドキュメントの他に、ウェブサイトのURLやコピーした文章を貼り付けることでも追加できますよ。一つのノートブックに、最大50個までの資料(ソース)を入れることができます。 - ステップ4:最初の質問をしてみる
資料の準備ができたら、いよいよAIとの対話の始まりです。画面の下にあるチャット欄に、資料について知りたいことを、話し言葉で自由に入力してみてください。「この資料を要約して」と入力するだけでも大丈夫です。 - ステップ5:AIの多彩な機能に触れてみる
質問をすると、AIが答えをくれるだけでなく、「こんな質問はどうですか?」と次の質問を提案してくれたり、資料全体の自動概要や、重要なポイントをまとめた「目次」を自動生成してくれたりします。まずはこの機能を試すだけでも、その賢さに驚くはずです。
ほら、なんだか私にもできそう!と思っていただけたのではないでしょうか。
コストを無駄にしない、無料・有料プランの賢い選び方
新しいことを始めるには、やはり予算のことが気になりますよね。特に、自治体での導入となると、費用対効果はとても大切なポイントだと思います。
嬉しいことに、NotebookLMは現時点(2025年9月3日)で、基本的にすべての機能を無料で利用することができます。ノートブックごとに最大50個のソース(資料)を追加できるなど、個人での資料整理や部署単位での試験導入には十分すぎる機能が備わっています。
出典: NotebookLM 公式サイト (
https://notebooklm.google.com/)
これを踏まえ、自治体における賢い導入ステップを2つのフェーズでご提案します。
- フェーズ1:
まずは「無料プラン」で実証実験(PoC)を行う まずはDX推進チームや、関心の高い数名の職員さんで無料プランを使い倒し、「どの業務で、どれくらいの効果が出そうか」という具体的な成果の仮説を立てることが大切です。これは、政府が推進する「サービス設計12箇条」の考え方にもある、利用者視点で小さく試して改善を繰り返すという、効果的な進め方です。この段階で「〇〇業務の時間を〇%削減可能」といった試算をまとめておきましょう。参考: サービスデザイン思考によるサービス・業務改革(BPR)を進めよう | 政府CIOポータル - フェーズ2:
将来的な「有料プラン」の登場に備え、費用対効果を試算する 今後、より高度な管理機能(例:庁内全体のアカウント管理、監査ログの取得)や、Google Workspaceとの連携を強化した「法人向け有料プラン」が登場する可能性は十分に考えられます。フェーズ1で得られた成果を基に、「もし年間〇万円のプランが出た場合、年間800時間の削減効果(舞鶴市の事例)と比較して導入価値はあるか?」といった具体的な費用対効果を試算しておけば、来年度の予算要求に向けた説得力のある資料を準備できるはずです。
AIの精度を劇的に変える、プロンプト設計の秘訣
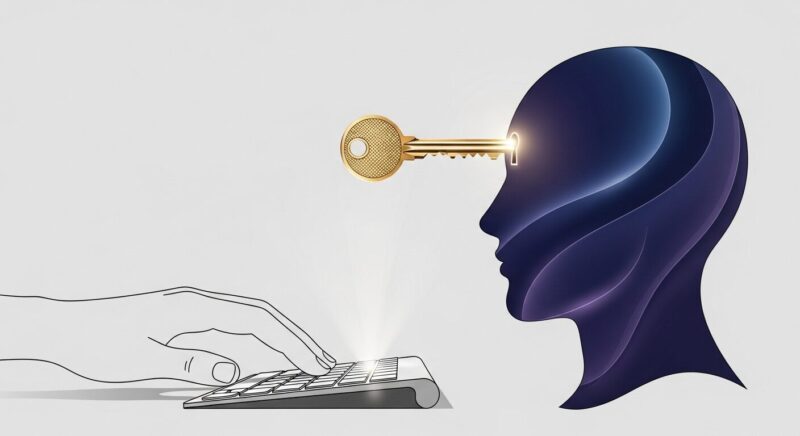
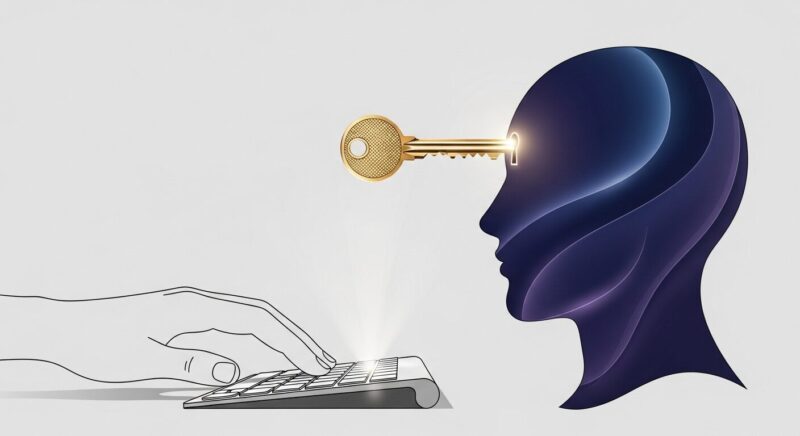
AIに質問してみたけれど、なんだか的外れな答えが返ってきて、「うーん、あまり使えないかも…」と感じた経験はありませんか?実はそれ、AIの性能が低いのではなく、私たちの「質問の仕方」に原因があることが多いんです。
AIから期待通りの答えを引き出すための「質問の呪文」、それが「プロンプト」です。AIとの対話は、優秀だけれど少し言葉足らずな新人の職員さんに、仕事のやり方を丁寧に教える感覚に似ています。具体的で分かりやすい指示(プロンプト)を出すことで、その性能を120%引き出すことができますよ。
ここでは、今日から使える4つの秘訣をお伝えしますね。
- 秘訣1:「役割(ペルソナ)」を与えてあげる
AIに「あなたは広報担当者です」「あなたはベテランのケースワーカーです」といった役割を与えるだけで、その役になりきって、より専門的で精度の高い回答をしてくれます。 - 秘訣2:「良い例(お手本)」を見せてあげる
何かを要約したり、言い換えたりしてほしい時は、一つお手本を示してあげるとAIはあなたの意図を正確に理解します。- 例:「以下の専門用語を、小学生にも分かるように言い換えてください。【例】『IoT』→『身の回りの色々なモノが、インターネットにつながること』。では、『DX』を言い換えてください。」
- 秘訣3:出力の「形式」を具体的に指定する
箇条書きなのか、表形式なのか、具体的な形式を指定してあげましょう。- 例:「あなたは重要な会議の内容をまとめるのが得意な秘書です。この議事録から、次のアクションに繋がる決定事項を3つ、箇条書きで抜き出してください。」
- 秘訣4:「思考のステップ」を順序立てて指示する
複雑な質問をする際は、私たちが頭の中で考える手順を、そのままAIに指示してみましょう。- 例:「まず、このアンケート結果から『公園の利用』に関する意見だけをすべて抜き出してください。次に、それらの意見を『要望』『不満』『感謝』の3つに分類してください。最後に、それぞれの分類で最も多かった意見を要約してください。」
「使われない」を防ぐ、庁内推進と定着のコツ
せっかく便利なツールを導入したのに、いつの間にか誰も使わなくなってしまった…。そんな経験はありませんか?これは、新しい変化に対して無意識に抵抗してしまう、私たちの「現状維持バイアス」という心の働きも関係しています。
NotebookLMを一部の職員だけの「流行りもの」で終わらせず、庁内全体の文化として定着させるには、少し工夫が必要です。大切なのは、トップダウンの指示だけでなく、現場から「使うと便利なんだ!」というポジティブな声が広がる仕組みを作ることです。経済産業省が発表している「DXレポート」でも指摘されている通り、DXの成功には経営トップのコミットメントと、現場を巻き込んだ推進体制が不可欠です。
そのための、具体的な4つのコツをご紹介します。
- コツ1:各部署に「楽しむ推進役(エバンジェリスト)」を置く
各部署からITに関心のある若手職員などを「NotebookLM推進役」に任命し、まずは自由にツールを探求してもらいます。彼らが「こんな面白い使い方を見つけたよ!」という発見を部署内で共有する、いわば楽しさを伝える伝道師(エバンジェリスト)になってもらうのです。 - コツ2:小さな「成功事例」の共有会(15分)を開く
月に一度、15分だけでもいいので、「うちの課では、〇〇の資料作成時間が半分に!」といった小さな成功事例を発表し合うオンライン会を開きましょう。他の部署の具体的な成功事例を聞くことで、「自分の業務でも使えるかも」という気持ちが自然と芽生えます。 - コツ3:「お助けテンプレート集」を育てる
便利なプロンプトのテンプレートや、「議事録要約用」「プレスリリース作成用」といった業務特化のノートブックのひな形を、庁内の共有フォルダに用意します。そして、推進役が見つけた便利な使い方を、皆でどんどん追加・更新していく「育てるテンプレート集」にすることがポイントです。 - コツ4:管理職が「使ってみてどう?」と声をかける
最も効果的なのは、課長などの管理職が、日々の業務の中で「あの件、NotebookLMで分析してみたらどう?」「使ってみてどうだった?」と積極的に声をかけることです。これにより、ツールの利用が「やっても良いこと」ではなく「推奨されること」なのだというメッセージが明確に伝わります。
周知・研修の「参照先」を固定しておくと定着が進みます。職員向けに安全に参照できる公式情報源をまとめたリストはこちら。


総括:【自治体担当者必見】NotebookLM導入前に確認すべき15の要点



最後までお読みいただき、ありがとうございました。
