 セキュア女子
セキュア女子「自治体で生成AIを比較したいけど、セキュリティが心配…」「一体何を基準に選べばいいの?」
わかります、その気持ち。 DX推進担当として、新しい技術にアンテナを張りながらも、そのリスクを考えると一歩踏み出すのに勇気がいりますよね。
「隣の市役所は、生成AIのおかげで定時退庁が当たり前になったらしい…」
なんて話を聞くと、私たちの職場もこの手作業に迫る静かな危機から抜け出さないと! と少し焦ってしまうかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
その焦りから、サービス選びを間違えてしまうと、職員の”善意”が招く、思わぬ情報漏えい事故につながる可能性もあるのです。
実は、便利な生成AIの裏には、まず知るべき『選定の落とし穴』が潜んでいます。 あなたは、AIが自信満々につく”もっともらしい嘘“を、きちんと見抜けますか?
でも、ご安心くださいね。
この記事では、そんなあなたの不安や疑問をすべて解消するために、失敗しない自治体の生成AI比較からで、どこよりも分かりやすく解説します。
導入までを3ステップ
- セキュリティ基準で比較して見つけるの選び方本命AIサービス5選
- 『安物買いの銭失い』を防ぐ費用対効果の見極め方
- 『これ入れて平気?』が分かる庁内ルール作りのコツ
そして、記事の最後には、稟議でそのまま使える、最後のチェックリストもご用意しました。
この記事を読み終える頃には、あなたの頭の中はスッキリ整理され、自信を持って次の一歩を踏み出せるはずですよ。
自治体の生成AI比較、まず知るべき『選定の落とし穴』
「隣は定時退庁…」手作業に迫る静かな危機
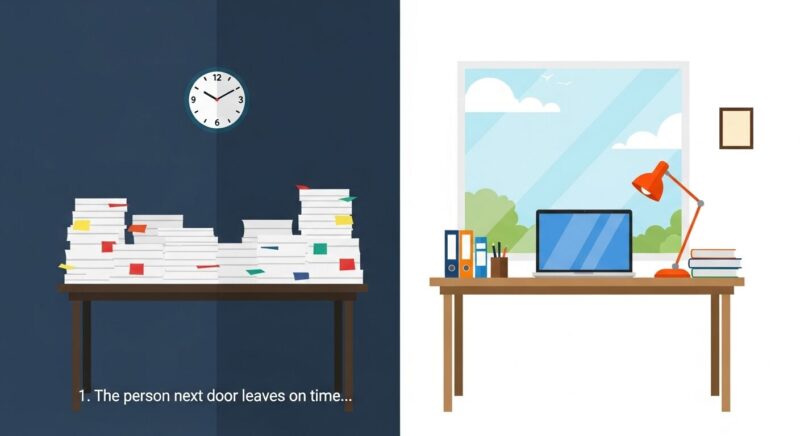
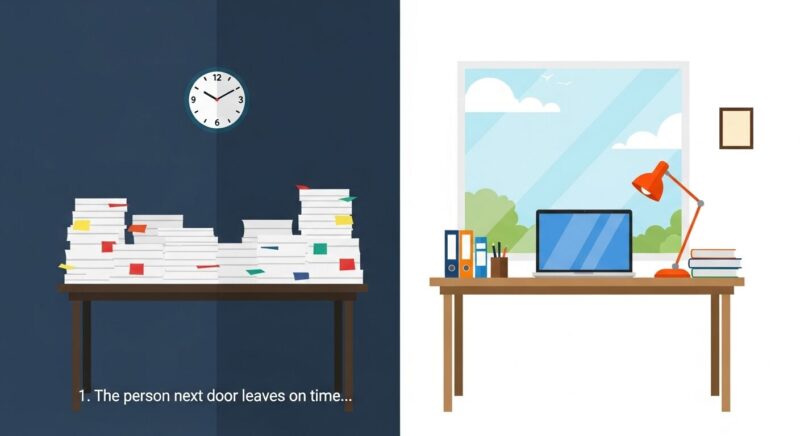
生成AIの導入を少しだけためらっている間に、実は自治体の業務効率には、気づきにくい大きな差が生まれ始めているかもしれません。 人口減少で職員数が限られる中、行政へのニーズは多様化・複雑化するばかり。 これは、まさしく「静かな危機」と言えるかもしれないですね。
なぜなら、一部の先進的な自治体では、既に生成AIを業務に活用して、これまで職員が多くの時間を費やしてきた作業を劇的に効率化しているからです。 その代表例が、国内の自治体で初めて全庁的にChatGPTの試行利用を開始した神奈川県横須賀市です。
PwCコンサルティングがまとめた市の効果測定レポートによると、イベントのアイデア出しや議事録の要約などにAIを活用した結果、職員の約8割が「業務での有用性を感じた」と回答し、文章作成などにかかる時間が1日あたり平均で約10分短縮されたという結果が出ています。 (出典:)横須賀市だけでなく、東京都をはじめとする多くの自治体でも同様の動きが加速しています。
もし、あなたの職場で今も多くの職員が深夜まで議事録の文字起こしや定型的な回答文の作成に追われているとしたら、その浮いた時間で他の自治体は、新たな子育て支援策を考えたり、防災計画の見直しを進めたりしている可能性があるのです。 このように、目に見えない「機会損失」はじわじわと広がっているのかもしれません。
だからこそ、日々の忙しさを理由に現状維持を選ぶのではなく、「私たちの職場も変われるチャンスがある」という視点を持つことが、今とても大切になっています。
職員の”善意”が招く、情報漏えい事故
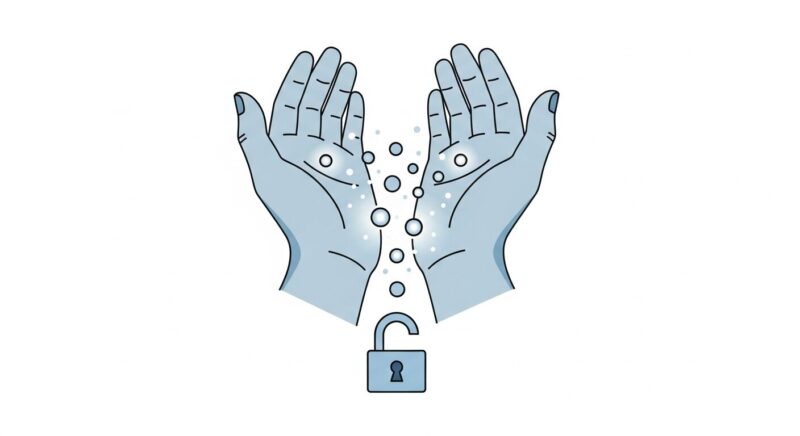
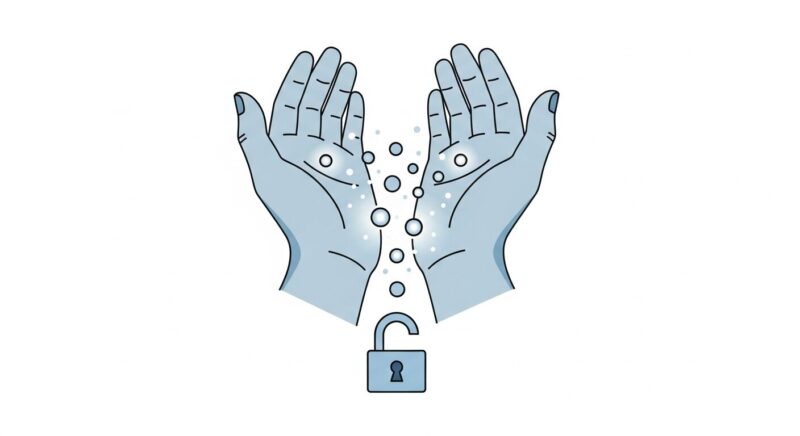
「少しでも業務を効率化して、住民サービスを向上させたい」という職員さんの真面目な気持ち、つまり”善意”が、予期せぬ情報漏えい事故の入り口になってしまうことがあるのをご存じでしたか?
その理由は、普段私たちが個人で使える無料の生成AIサービスの多くが、入力された情報をサービス改善(AIの性能向上)のために学習データとして利用する可能性があるからです。 これはサービスの利用規約に明記されていることが多いのですが、つい「同意する」のボタンを押してしまいがちですよね。
例えば、ある会議の議事録を要約してもらおうと、参加者の氏名や、まだ公開されていない人事情報などが含まれた文章を、そのままコピー&ペーストしてしまったと想像してみてください。 その情報がAIの学習に使われると、将来的に全く別の誰かの質問に対し、入力した情報の一部が回答として生成され、結果的に公の情報になってしまうリスクがあります。
これは、個人情報保護法で定められた自治体の義務や、住民からの信頼を根底から揺るがしかねない事態です。
総務省の公表では、情報資産を機密性に応じて3段階以上に分類し、最も重要な「機密性3」の情報は厳格に管理するよう求めています。 地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン
このように、職員一人ひとりの意識に頼るだけでは限界があります。 組織として「このAIツールなら入力情報を学習されないから、安心して使える」という安全な環境をしっかりと用意してあげることが、”善意”による事故を未然に防ぐために不可欠なのです。
AIの”もっともらしい嘘”、見抜けますか?
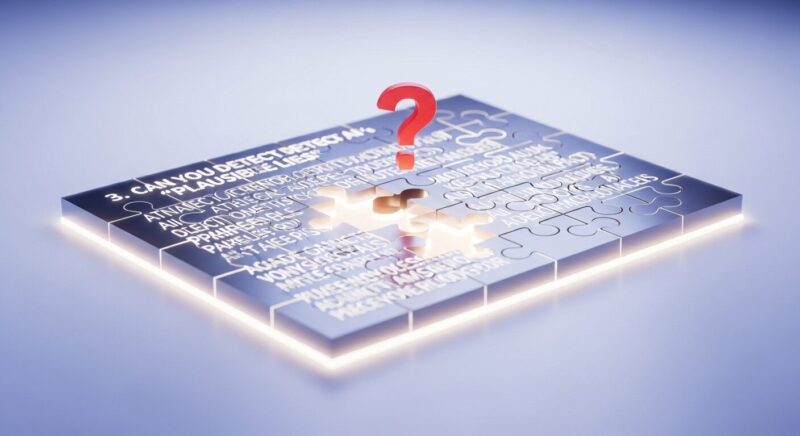
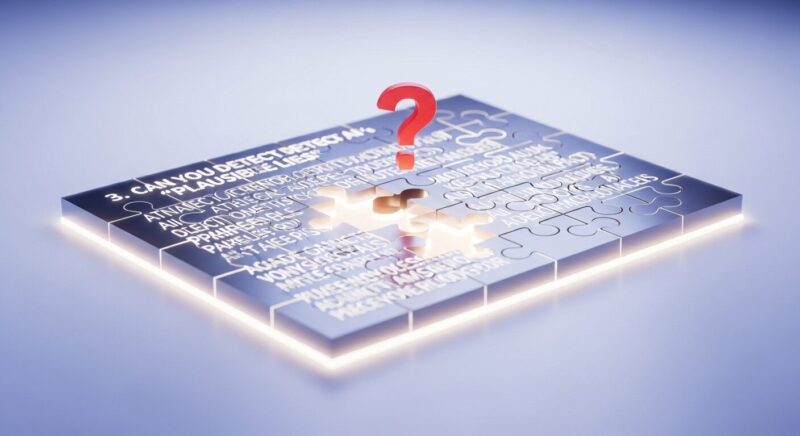
生成AIは本当に優秀なアシスタントですが、時々、事実とは全く異なる”もっともらしい嘘”を、まるで真実であるかのように回答することがあります。 あなたは、その嘘をきちんと見抜く自信がありますか?
この現象は「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれていて、AIが持つ技術的なクセのようなものです。 AIは、文章の正しさを理解して回答しているわけではなく、過去に学習した膨大な情報の中から「統計的に最もそれらしい言葉の繋がり」を予測して文章を作り出しているため、どうしても事実に基づかない情報が生成されてしまうことがあるのですね。
具体的には、「〇〇市の新しい子育て支援制度について、対象者と申請方法を教えて」とAIに質問したとします。 するとAIは、昨年度の古い情報や、隣の市の制度内容を巧妙に組み合わせるなどして、存在しない架空の制度を、自信満々に説明してしまうかもしれません。 内閣府の「」でも、生成AIの利用リスクとしてこの点が指摘されており、利用者が情報の真偽を確認(ファクトチェック)することが極めて重要だと注意を促しています。
もし、このAIの回答を信じて住民の方へのお知らせを作成してしまったら、大きな混乱を招き、自治体への信頼を大きく損なうことになりかねません。 AI戦略会議
このような理由から、AIの答えを100%鵜呑みにするのはとても危険です。 AIはあくまで「優秀なアイデア出しの相手」や「下書き作成アシスタント」と捉え、最終的な事実確認と判断は必ず私たち人間が行う、というルールを徹底することが、AIと上手に付き合っていくための大切な心構えになります。
失敗しない自治体生成AI比較、導入まで3ステップ
【セキュリティ基準で比較】本命AIサービス5選


生成AIに潜むリスクが分かると、今度は「じゃあ、一体どのサービスなら本当に安心して使えるの?」という点が気になりますよね。 ここでは、自治体向けサービスを選ぶ上で絶対に外せない、セキュリティ基準の観点から見た「本命」を見つけるための、5つのチェックリストをお伝えします。
大切なのは、特定のサービス名に飛びつくのではなく、「なぜそれが安全なのか」という判断基準を、あなた自身が持つことです。
【自治体向けAI】安心の5か条チェックリスト
LGWAN環境
インターネットから分離された閉域網で利用できるか
学習利用の禁止
入力した機密情報がAIの学習に使われないことが明記されているか
国内でのデータ管理
データが日本の法律が適用される国内で管理されているか
他の自治体での実績
多くの自治体で実際に利用されている信頼性があるか
導入後のサポート
職員向けの研修や質問対応などの体制が整っているか
【自治体向けAI・安心の5か条チェックリスト】
- LGWAN環境で利用できるか?
- 入力情報をAI学習に利用しないと明記されているか?
- データは国内で管理されているか?
- 他の自治体での導入実績は豊富か?
- 職員向けのサポート体制は整っているか?
特に重要なのが、1番目の「LGWAN」です。 これは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営する、インターネットから完全に切り離された自治体専用のネットワーク(閉域網)のことです。 この中で動くサービスは、外部からの不正アクセスなどのリスクを原理的に大きく下げることができます。 また、データが国内で管理されていることは、日本の法律が適用される安心感にも繋がりますね。 これらの基準をクリアしているサービスの中から、あなたの自治体の業務内容や予算に合うものを選んでいくことが、失敗しないための賢い第一歩になりますよ。 J-LIS 総合行政ネットワーク(LGWAN)
『安物買いの銭失い』を防ぐ費用対効果


セキュリティの高いサービスを選ぶとなると、どうしても気になるのが「費用」の問題だと思います。 月額料金だけを見ると、つい安いプランに目が行きがちですが、ここで少し立ち止まってみてください。 もしかしたら、その選択が『安物買いの銭失い』になってしまうかもしれません。
その理由は、目に見えるライセンス料の裏に隠れた、「時間」という最も貴重な資産価値を見逃してしまうからです。 例えば、前述の横須賀市の例では1日平均10分の時間短縮でしたが、仮に活用が進み、職員一人あたり平均で1日30分の作業時間を短縮できたと試算してみましょう。 時給2,000円の職員さんなら、1ヶ月(20日勤務)での時間価値が生まれます。 もし100人の職員が同じ効果を得られれば、それだけでの効果です。 20,000円分月々200万円相当
これは単なる経費ではなく、創出された時間で『より質の高い住民サービス』を生み出すための、未来への投資なのです。
月額費用 VS 生まれる時間価値
月額費用(コスト)
セキュアなAIサービスのライセンス料
数十万円〜
時間創出(価値)
職員100人が1日30分時短した場合
月200万円相当
逆に、無料だからとセキュリティが曖昧なツールを導入した結果、職員が不安で使わなかったり、情報システム部門の問い合わせ対応に追われたり、万が一の事故で信頼を失ったりすれば、その損失は計り知れません。 だからこそ、表面的な価格だけでなく、生まれる時間価値と住民サービスの向上まで含めた長期的な視点で費用対効果を考えることが、後悔しない選択のためにとても大切になります。
『これ入れて平気?』が分かる庁内ルール作り
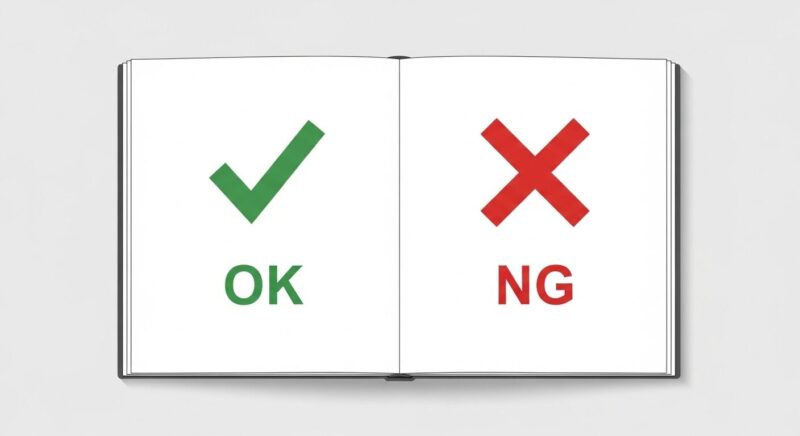
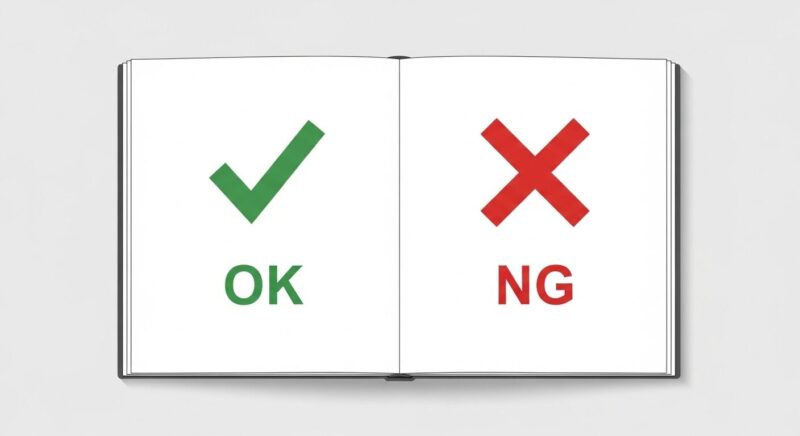
さて、導入するAIサービスも決まり、いよいよこれから、という段階で必ず用意したいのが、庁内での「共通ルール」です。 なぜなら、ルールがないと真面目な職員さんほど「万が一、情報漏えいしたら自分の責任になるかも…」と不安に感じ、せっかくの便利なツールを十分に活用できないという、もったいない状況が生まれてしまうからです。
この不安を解消するために、何十ページもある分厚いマニュアルは必要ありません。
💡 あわせて読みたい
庁内ルールづくりの前提になる、LGWAN対応や「入力情報を学習に使わない」などのセキュリティ論点をもう一歩深掘りしたい方はこちら。実務のチェックポイントをギュッと整理しています。


総務省が公表している「」でも、利用ルールの明確化と継続的な見直しが推奨されています。大切なのは、誰でもすぐに判断できる「A4用紙1枚」にまとまるような、シンプルで分かりやすいルールです。 地方公共団体における AI 利活用ガイドブック
例えば、こんな3つの柱でルールを作ってみてはいかがでしょうか。
- 【禁止リスト】🚫これだけは絶対に入力しない!
- 氏名、住所、マイナンバーなどの個人情報
- 議会で公開される前の議案情報や人事情報
- 【利用の心得】AIの回答、こう使おう!
- AIの回答は「下書き」と心得る。 必ず元の資料や根拠条例を確認すること。
- 住民へのお知らせに使う前は、必ず所属長(上司)のチェックを受けること。
- 【困ったときは】迷ったら一人で悩まない!
- 入力して良いか迷う情報は、まず情報システム部門へ相談すること。
このように、具体的な行動レベルまで落とし込んだシンプルなルールがあれば、職員の皆さんは安心してAIの能力を引き出すことができます。 ツールという「道具」を渡すだけでなく、その「安全な使い方」もセットで届けてあげることが、導入担当者としての大切な役割ですね。
【まとめ】稟議で使える、最後のチェックリスト


ここまで、自治体での生成AI導入に潜む「静かな危機」から、具体的なサービスの選び方、そして庁内での活用方法までを見てきましたが、いかがでしたか? 最後にこの記事の要点を、あなたが上司や関係部署に自信を持って説明するための「稟議の骨子」として使えるチェックリストにまとめました。
【そのまま使える】生成AI導入 稟議のための最終確認リスト
- なぜ「今」必要なのか? (課題の明確化)
現状の手作業を続けた場合の「見えない損失(機会損失)」と、AI導入で他自治体が成果を上げている事実を具体的に説明できるか? - なぜ「このサービス」が安全なのか? (リスク対策)
情報漏えいやハルシネーションのリスクを理解した上で、LGWAN対応など、なぜこのサービスがセキュリティ基準を満たしているのかを明確に説明できるか? - 費用を「上回る価値」は何か? (投資対効果)
月額費用だけでなく、職員の時間創出効果を具体的に試算し、導入が単なる「経費」ではなく、住民サービスの向上に繋がる「未来への投資」であることを伝えられるか? - どうすれば「全庁で」使われるのか? (導入後の計画)
職員が安心して使えるシンプルな庁内ルールを用意し、導入して終わりではなく、活用を定着させるまでの道筋を示せているか?
この4つの問いに、あなたの言葉で具体的な答えを書き込めたなら、その稟議書はもう完成したも同然です。 あなたの提案は、きっと同僚や上司の心を動かし、自治体の未来を変える力になるはずです。 この記事が、あなたの自治体の明るい未来に向けた、新しい一歩を踏み出すきっかけになれたら、とても嬉しいです。
総括:自治体生成AI導入で失敗しないための重要ポイント



最後までお読みいただき、ありがとうございました。
