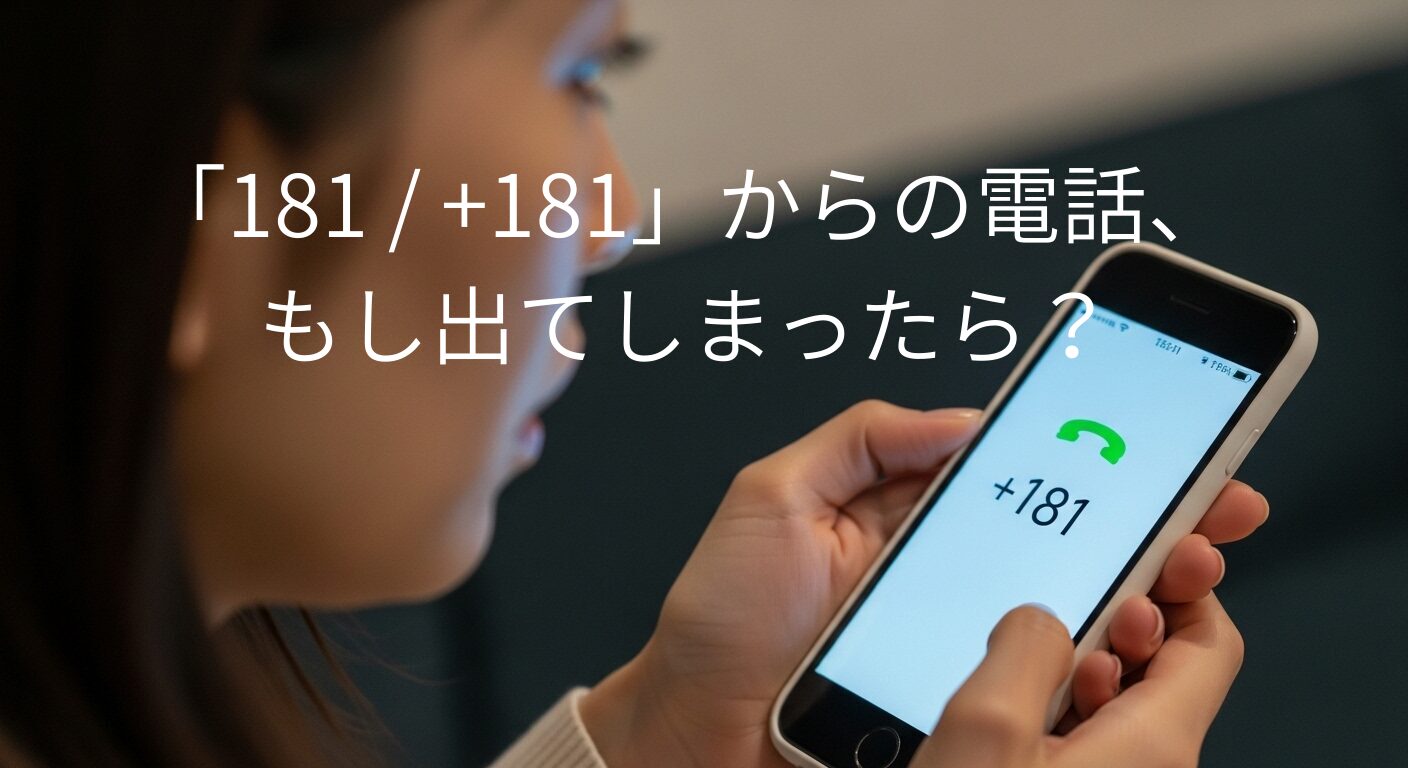プルルル…スマホに見慣れない「181」からの着信。
 ゆうま
ゆうま「え、これって何…?出てもいいの?もしかして詐欺電話…?」
スマホに突然表示される「181」や「+181」からの着信、ドキッとしますよね。「これって一体なに?」と不安になって検索したあなた、その直感は正しいです。というのも、この番号には実は気をつけるべきポイントがいくつかあるんです。
この記事では、謎の着信「181」の正体と、天気予報なのか詐欺なのかという疑問に答えていきます。
それだけじゃありません。うっかり出てしまった時にすぐやるべき3つのこと、折り返してしまった時の対処法、「当選しました」系の危険な詐欺手口、業務中の着信への対応など、実践的な内容をまとめました。
さらに、「無視すればいい」が実は正解じゃない理由、電話番号が知らないうちに流出してしまう意外なルート、iPhone/Androidそれぞれの効果的なブロック設定まで、具体的に解説します。
この記事を読み終わる頃には、不審な電話に怯える必要はなくなっているはずです。正しい知識があれば、あなたも大切な家族も守れます。今日からできる対策、一緒に見ていきましょう。
 しろ
しろ管理者として通信ログを見ると、この「+」は海外経由の証拠。日本の番号に見せかけた巧妙な偽装(スプーフィング)なんです。
折り返すとその瞬間に高額な国際通話料が発生する仕組みなので、技術的にも「完全無視」が唯一の正解なんですよ。
「なぜ番号がバレているの?」と不安ではありませんか?
不審な電話の後は、SMSによるフィッシング詐欺が届くリスクも急増します。
まずはスマホのセキュリティを強化し、個人情報の流出を防ぎましょう。
※動作が軽く、詐欺サイト対策にも最強です
- 謎の着信「181」と「+181」の危険性を、正しく見分けられるようになる
- もし電話に出てしまっても、慌てず冷静に、そして正しく行動できるようになる
- 「当選」や「未納料金」といった、よくある詐欺の口実にもう騙されなくなる
- 自分と大切な家族を、未来の危険から守るための具体的な予防策がわかる
謎の着信「181」の正体と緊急時の対処法
- 天気予報?詐欺?「+」の有無で見分ける
- うっかり出てしまった時の3ステップ
- 折り返してしまった時の緊急対処法
- 「当選」は危険!最新の詐欺手口
- 業務中の着信、正しい対応とは?
天気予報?詐欺?「+」の有無で見分ける

「181」からの着信、その正体不明さに不安を感じますよね。 この問題の核心は、「そもそも、なぜその番号から着信があるのか?」という点にあります。
まず、日本の電話番号制度において、「181」という3桁の番号は、一般向けの特定の電話サービスとして割り当てられていません。 つまり、NTTなどの通信事業者が「181」という番号から、あなたのスマホへ電話をかけてくることは通常ありえないのです。 この事実から導き出される結論は一つ。あなたのスマホ画面に「181」と表示された場合、その番号は第三者によって偽装(スプーフィング)されている可能性が極めて高い、ということになります。
そして、さらに警戒レベルが上がるのが「+181…」のように「+」から始まる番号です。 この2つの違いを、下の表でしっかり確認しておきましょう。
| 着信番号「181」 | 着信番号「+181…」 | |
|---|---|---|
| 正体 | 偽装された不審な電話 | 海外(国番号+1)からの不審な国際電話 |
| 危険性 | 不明な相手からのため高リスク | ワン切り詐欺等で悪用される典型的な手口 |
| 対処法 | 無視・着信拒否 | 絶対に無視・着信拒否・折り返さない |
「+181…」は、「+1」(アメリカやカナダなどの国番号)の国から発信され、市外局番以降の番号が偶然「81」から始まっている電話番号です。 これは、受信した人が日本の国番号「+81」と見間違えたり、関連性を疑ったりすることを狙った、非常に紛らわしい手口と言えます。
もちろん、「+1」から始まるすべての電話が危険な訳ではありませんが、「+181」で始まる番号は、高額な通話料を狙った「国際ワン切り詐欺」で頻繁に悪用されるパターンとして広く知られています。 かけ直してしまうと、海外の有料サービスに繋がり、数秒話しただけで数千円といった高額な国際通話料金を請求される危険性があるのです。
そのため、心当たりのない「+」から始まる国際電話、とりわけ「+181」で始まる番号には最大限の警戒が必要です。
あわせて読みたい
「+」「8」から始まる表示の見分け方をもう少し具体的に押さえておきたい方はこちらもどうぞ。桁数・表示パターン別に3秒チェックできます。

この手口については、国民生活センターや警察庁からも繰り返し注意喚起がなされています。 もし不審な国際電話で料金請求をされたり、不安に感じたりした場合は、一人で悩まずに以下の公的な相談窓口を利用しましょう。
- 消費者ホットライン:「188(いやや!)」
全国の消費生活センターや相談窓口を案内してくれる、消費者トラブルの統一ダイヤルです。契約や請求などお金に関するトラブルはこちらに相談してください。 - 警察相談専用電話:「#9110」
詐欺や犯罪の可能性があると感じた場合の相談窓口です。「犯罪かもしれない」と不安になったら、こちらに電話しましょう。
うっかり出てしまった時の3ステップ

もし、うっかり不審な電話に出てしまっても、まずは深呼吸してください。大丈夫、冷静に対処すれば何も問題はありません。 被害をゼロに抑えるための、「魔法の4ステップ」をご紹介しますね。
相手は、あなたが応答することで「この電話番号は現在使われている」と確認し、新たな詐欺のターゲットリストに加えようとします。 それだけでなく、あなたの「はい」という返事の声を録音し、悪用しようとする「ビッシング(ボイス・フィッシング)」のリスクも潜んでいます。だからこそ、すぐに行動することが大切なのです。
ステップ1:とにかく、何も話さず電話を切る
「もしもし」や「はい」といった返事も不要です。相手が何か話していても、無言のまま、すぐに通話終了ボタンを押してください。これが最も重要な最初の行動です。
ステップ2:その番号を「着信拒否」に設定する
同じ番号から二度とかかってこないように、スマートフォンの着信拒否リストに追加しましょう。設定方法は機種によりますが、「通話履歴」から簡単に設定できる場合がほとんどです。
ステップ3:電話番号を検索してみる
少し落ち着いたら、かかってきた電話番号をコピーして、Googleなどで検索してみてください。 「080-XXXX-XXXX 迷惑電話」のように検索すると、同じ番号からの着信に悩まされている人の口コミが見つかることがあります。詐欺だと確信できれば、少し安心できますよね。
ステップ4:不安なら、専門家に相談する
「何か個人情報を言ってしまったかも…」と後から不安になった場合は、一人で抱え込まないでください。警察の相談専用窓口「#9110」 に電話すれば、専門の相談員があなたの状況に合わせたアドバイスをくれます。
折り返してしまった時の緊急対処法
「つい、かけ直してしまった…」 一瞬の気の緩みで、後から大きな不安に襲われてしまいますよね。でも、大丈夫。ここからの行動が何よりも大切です。 大切なのは、パニックにならず、しかし迅速に行動することです。 以下に、緊急時のアクションプランをまとめました。
ステップ1:利用明細をリアルタイムで確認する
まずは、ご契約の携帯電話会社(docomo、au、ソフトバンクなど)の公式アプリやマイページにログインし、「通話履歴」や「未確定料金」を確認しましょう。 国際電話の料金は、データ通信料などと違ってすぐに反映されない場合もあります。一度確認して何もなくても、翌日などにもう一度確認してみてください。
ステップ2:携帯電話会社のサポートに連絡する
少しでも不審な料金や履歴を見つけたら、すぐにサポートセンターに電話しましょう。伝えるべきポイントは以下の通りです。 「心当たりのない国際電話番号に、誤って折り返し発信してしまいました。いわゆる『国際ワン切り詐欺』の可能性がないか、また高額な通話料が発生していないか確認をお願いします。」 誠に残念ながら、一度発生してしまった通話料の取り消しは難しい場合が多いですが、被害を報告し、相談することが非常に重要です。
ステップ3:公的な専門機関に相談する
金銭的な被害が発生してしまった場合や、契約に関するトラブルに発展しそうな場合は、前述の通り、専門の公的機関へ相談することが大切です。 このようなお金のトラブルについては、消費者ホットライン「188(いやや!)」があなたの強い味方になってくれますよ。
電話番号が知られると、次は「宅配便不在通知」や「料金未納」を装った偽SMSが届く危険性が急増します。
うっかりURLを押して被害に遭う前に、セキュリティソフトでブロック設定をしておきましょう。
※Android版には着信・SMSフィルター機能も搭載
「当選」は危険!最新の詐欺手口

「現金100万円が当選しました」「サイトの未納料金があります」 こうした、あなたの感情を大きく揺さぶる突然の電話は、残念ながら詐欺である可能性が極めて高いです。
詐欺師たちは、私たちの「もしかしたら本当かも」という期待感や、「大変なことになるかも」という焦りの気持ちを巧みに利用します。 そして、その最終目的は、手数料や解決金といった名目で「コンビニで電子マネーカードを買って、番号を教えて」と指示すること。これが典型的な危険信号です。
なぜなら、一度番号を教えてしまった電子マネーは、すぐに換金されてしまい、追跡や返金がほぼ不可能だからです。
- 「当選金を受け取るための登録料として…」
- 「サイトの未納料金の支払いとして…」
- 「訴訟を取り下げるための和解金として…」
これらは全て、あなたをだますための口実に過ぎません。 警察庁の発表によると、令和5年中(2023年)の特殊詐欺全体の被害額は約441.2億円にも上り、このような「架空料金請求詐欺」の被害も後を絶ちません。 (出典:警察庁 特殊詐欺対策ページ ※サイト内の統計資料等から最新の状況をご確認いただけます)
「当選した」という嬉しいニュースを信じたい気持ち(確証バイアス)はとてもよく分かりますが、公的機関や大手企業が、支払いをコンビニの電子マネーカードで要求することは、絶対にありません。 この一点を覚えておくだけで、多くの詐欺を防ぐことができます。
業務中の着信、正しい対応とは?

会社の電話に不審な番号から着信があった場合、あなたの対応一つが、会社全体を守る盾になります。 個人のスマートフォンとは違い、会社の電話は企業の重要な情報に繋がる入り口。近年では、電話でのやり取りから情報を巧みに盗み出す「ソーシャルエンジニアリング」という手口も増えています。
「もし大事な取引先だったら…」と不安になる気持ちは分かりますが、基本は「心当たりのない番号には出ない」です。本当に重要な用件であれば、留守番電話にメッセージを残したり、メールで連絡してきたりするはずです。
万が一、うっかり電話に出てしまった場合は、以下の「守りの4ステップ」を徹底してください。
ステップ1:社名や個人名は名乗らない
「お電話ありがとうございます」といった中立的な挨拶に留め、会社名や部署名、ご自身の名前を先に名乗るのは避けましょう。
ステップ2:相手の情報を鵜呑みにしない
「〇〇社の者ですが」と名乗られても、すぐに信用してはいけません。「担当者の名前は?」「部署名は?」など、こちらから情報を聞き出そうとせず、相手の用件を冷静に聞くことに徹します。
ステップ3:安易に情報を与えず、丁寧に断る
担当者の在席確認や内線番号、メールアドレスなどを聞かれても、「あいにく分かりかねます」「個人情報に関わるためお答えできません」と、丁寧にはっきりと断り、電話を切りましょう。
ステップ4:必ず上司や担当部署に報告する
どんなに些細な内容でも、不審な電話があった事実は必ず上司や総務・IT部門に報告してください。 あなたへの一本の電話が、会社全体を狙った攻撃の始まりかもしれません。情報を共有することで、会社として着信拒否設定をしたり、全社員に注意喚起したりと、組織的な防御策を講じることができます。
もう騙されない。「181」から身を守る予防策
- iPhone/Androidの最強ブロック設定
- なぜ?電話番号が流出する意外なルート
- 「無視」は最善策ではない意外な理由
- 家族を守るための公的相談窓口
iPhone/Androidの最強ブロック設定

しつこい迷惑電話、本当にウンザリしますよね。 ブロックしても次々と番号を変えてくる「いたちごっこ」に、終わりが見えないと感じていませんか?
実は、あなたのスマートフォンに標準で備わっている機能を使えば、いわば「デジタルな門番」を立てて、知らない相手からの着信をまとめてシャットアウトできるんです。
【iPhoneの場合】「不明な発信者を消音」機能
- 「設定」アプリを開き、下にスクロールして「電話」をタップします。
- 「不明な発信者を消音」という項目を見つけてタップします。
- スイッチを「オン(緑色)」に切り替えます。
これだけで設定は完了です。 今後、あなたの連絡先に登録されていない番号からの着信は、呼び出し音が鳴らずに直接「留守番電話」に送られ、「通話履歴」には記録として残ります。
【Androidの場合】「不明な番号をブロック」機能
Androidは機種によって操作が少し異なりますが、基本的な手順は同じです。
- 標準の「電話」アプリを開きます。
- 右上のメニューボタン(︙など)から「設定」を開きます。
- 「ブロック中の電話番号」や「ブロック設定」といった項目をタップします。
- 「不明な番号」や「非通知設定の番号」をブロックするスイッチを「オン」にします。
⚠️ 設定する前に知っておきたい注意点
この設定は非常に強力ですが、一つだけ注意点があります。 それは、あなたが連絡先に登録していない、全ての番号からの着信が通知されなくなるということです。
例えば、以下のような重要な電話も逃してしまう可能性があります。
- 宅配便のドライバーさんからの配達前の連絡
- 病院やクリニックからの予約確認の電話
- 新しい仕事の取引先からの初めての電話
- お子さんが友達の家の電話からかけてきた緊急の連絡
そのため、この機能をオンにした場合は、「留守番電話」と「通話履歴」をこまめにチェックする習慣をセットで身につけるようにしましょう。
電話が鳴るのは、あなたが知っている人からだけ。それだけで、日常のストレスが大きく減りますよ。
なぜ?電話番号が流出する意外なルート
「そもそも、どうして私の電話番号が知られてしまったの?」 そう不思議に思いますよね。実は、私たちの電話番号は、自分でも気づかないうちに、日常に潜むいくつかの「落とし穴」から漏れてしまっている可能性があるんです。 「自分だけは大丈夫だろう」という無意識の思い込みが、一番の落とし穴かもしれません。
あなたの番号は大丈夫か、3つのルートを一緒に確認してみましょう。
ルート1:無料アプリや懸賞サイトへの登録
「無料」「診断」「懸賞」といった言葉に惹かれてサービスを利用する際、利用規約やプライバシーポリシーをよく読まずに「同意」ボタンを押していませんか? その小さな文字の中に、「取得した個人情報を第三者に提供することがあります」という一文が紛れ込んでいるケースは少なくありません。
- 【対策】:同意ボタンを押す前に、規約の中で「第三者提供」「共同利用」といったキーワードがないか、一度確認するクセをつけましょう。
ルート2:SNSのプライバシー設定
FacebookやInstagramなどのプロフィールに、電話番号を登録していませんか?その公開範囲が「全体に公開」になっていると、誰でもあなたの番号を閲覧できてしまいます。 また、過去に連携したアプリが、あなたの許可のもとで情報を保持している可能性もあります。
- 【対策】:今すぐ、お使いのSNSすべてのプライバシー設定を見直しましょう。電話番号の公開範囲は「自分のみ」に設定するか、不要であればプロフィールから削除するのが最も安全です。
ルート3:利用サービスからの情報漏えい
これは、私たち自身がどれだけ気をつけていても、残念ながら防ぎきれないルートです。 過去に利用したネットショップや会員サービスを提供している企業がサイバー攻撃を受け、顧客情報が流出してしまうケースです。 実際に、個人情報保護委員会には、企業からの個人情報漏えいに関する報告が年間で数千件も寄せられています。 (公式サイト:個人情報保護委員会)
- 【対策】:漏えいそのものを防ぐのは困難ですが、被害を最小限に抑えることは可能です。サービスごとに異なるパスワードを設定し、使い回しをしないようにしましょう。
「無視」は最善策ではない意外な理由
「知らない番号は、とにかく無視するのが一番安全」 そう思っていませんか?もちろん、それは間違いではありませんが、実はそれだけでは万全とは言えない、少し怖い落とし穴があるんです。
むしろ、あなたが電話を「無視」したその瞬間も、相手にとっては「この番号は使える!」という貴重な情報になってしまうのです。
これは、詐欺グループが「ロボコール」というシステムを使い、コンピューターで無数の電話番号に自動発信して、「現在使われている有効な番号リスト」を作成しているためです。 一度でも呼び出し音が最後まで鳴ったり、留守番電話に繋がったりすると、「応答あり」と機械が判断。その結果、どうなるかというと…。
- あなたの番号が「アクティブな番号」として、迷惑電話リスト内での価値が上がる。
- 別の詐欺グループに、そのリストが高値で売買される。
- 今度は、より巧妙な迷惑SMS(ショートメッセージ)が大量に届くようになる。
実際に、宅配業者などを装った悪質なフィッシングSMSの被害は後を絶たず、総務省も繰り返し注意を呼びかけています。 (出典:総務省 フィッシングSMSや不審なメール等に注意)
ですから、ただ「無視」するだけでなく、前述の「不明な発信者を消音(ブロック)」設定を組み合わせることが不可欠です。 「無視」を玄関の鍵だとすれば、「ブロック設定」は敷地全体を囲む高い塀のようなもの。この2つを組み合わせることで、初めて「鉄壁の守り」が完成すると言えるでしょう。
家族を守るための公的相談窓口

ご自身の対策が完璧になっても、心のどこかで消えない心配。それは、大切なご家族、特にご両親のことではないでしょうか。
詐欺師は、電話に出たら丁寧に話を聞いてしまう、人の善意や少しの判断の迷いにつけ込むプロです。だからこそ、私たちにできることがあります。それは、困った時に頼れる場所を「見える化」して、物理的なお守りを渡してあげることです。
今日からできる、家族を守る2つのアクション
1. 「合言葉」を決めておく
まず、実家に帰った際などに、「最近、変な電話ない?」と声をかけることから始めましょう。そして、「もし電話で『電子マネーを買ってきて』って言われたら、それは100%詐欺だから、すぐに電話を切って私に連絡してね」という家族だけの「合言葉」を決めておくのが効果的です。
最近は“家族の声”まで悪用されます。合言葉の決め方や、違和感の見抜き方を具体例で押さえておきましょう。
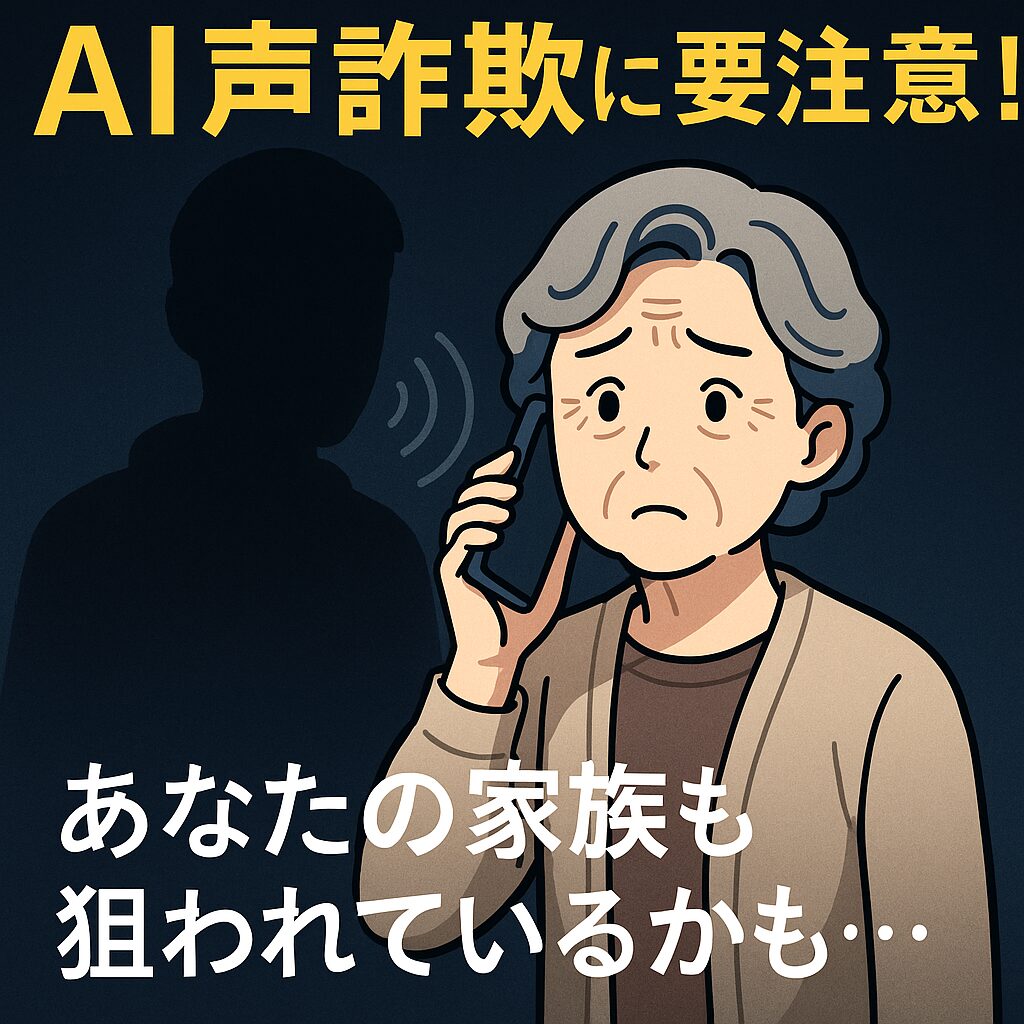
2. 「お守りメモ」を電話のそばに貼る
これが最も強力な対策かもしれません。実家の固定電話など、電話機のすぐそばに、大きな文字で書いた注意書きのメモを貼っておくのです。
<メモに書く内容の例>
- 知らない番号には出ない!
- 「お金」「電子マネー」の話が出たら詐欺!すぐに切る!
- 困ったら、まずここに電話
- 警察相談:#9110
- 消費者ホットライン:188
覚えておきたい2つの公的相談窓口
もしもの時のために、2つの相談窓口の役割の違いを改めて確認しておきましょう。
| 機関名 | 相談内容 | 相談窓口(電話番号) |
| 警察 | 詐欺や犯罪の疑い、身の危険を感じた時 | 警察相談専用電話「#9110」 |
| 国民生活センター | 契約・請求トラブルなど、消費者問題全般 | 消費者ホットライン「188(いやや!)」 |
(出典:警察庁 相談窓口のご案内)
【最終チェック】もう迷わない!不審な電話からあなたを守る知識
- 「181」からの着信は、番号が偽装された不審な電話である
- 「+181」は海外からかかってくる国際電話で、詐欺の可能性が高い
- 折り返し電話は、高額な通話料を狙ったワン切り詐欺だ
- うっかり出ても、声が悪用される危険があるため無言ですぐに切る
- 出てしまったら即切りし、その番号を着信拒否するのが基本対処
- 万が一折り返したら、まず携帯会社の利用明細をすぐに確認する
- 金銭被害や契約トラブルは消費者ホットライン「188」へ相談
- 「当選した」という電話は電子マネーを要求する典型的な詐欺
- 公的機関が支払いにコンビニの電子マネーを要求することは絶対にない
- 会社の電話では社名や個人名を名乗らず、すぐに上司へ報告する
- スマホの「不明な発信者を消音」機能は迷惑電話対策に有効である
- ただし重要連絡を逃すリスクがあり、留守電等の確認は必須である
- 無料アプリの安易な利用規約同意が、情報流出の一因となる
- SNSに登録した電話番号は「自分のみ」に公開設定を見直す
- 電話を無視するだけでも番号の有効性が伝わり、被害が拡大する
 しろ
しろ最後までお読みいただき、ありがとうございました。